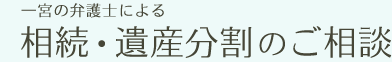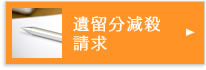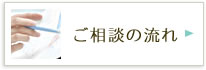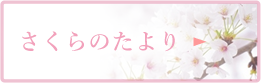成年後見人になることができない人は以下のように定められています。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者
以上の欠格事由に該当しなければ、特別な資格がなくとも後見人になることができます。
【重要】親族後見人と専門職後見人
子どもや兄弟姉妹などの親族が後見人となるケースは全体のおよそ42%を占めていますが(平成25年司法統計)、親族が後見人となるケースが全体に占める割合は、年々減少しています。
これは大変残念なことですが、親族後見人による横領などの不正事件が多発しているため、財産管理に注意が必要な事案や、ある程度まとまった資産がある事案では、裁判所が弁護士等の専門職後見人を選任するケースが増えているためです(→「成年後見人の不正について」)。
申立人は、成年後見の後見人候補者を指名することができ、申立人が親族の場合、自分自身やその他の親族を候補者に挙げることも一般的ですが、いざ裁判所から親族後見人は認めないとされても、一旦裁判所に受理された申立は取り下げることができません。
従って、親族後見人を予定して申し立てたものの、採用されなかった場合、親族申立人にとっては誰が後見人になるか分からないまま、裁判所の判断で後見人が選任されてしまうことになります。
例えば、子どもが認知症になった親のために自分が後見人になろうとして申し立てたところ、裁判所の判断で見ず知らずの専門職後見人が選任され、親の財産をすべて預けなければならないということにもなるのです。
こうした事態を回避するため、専門職後見人が選任される可能性の高い事案では、申立人が信頼している弁護士に申立手続を依頼し、後見人候補者となってもらうことも検討した方がよいでしょう。