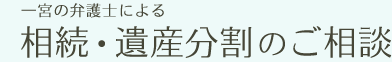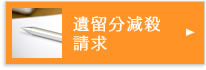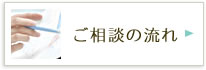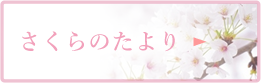被相続人の預金を、相続人の1人が勝手に引き出して使い込んでしまったというケースはよくあります。このようなケースでは、どのように処理をすればいいのでしょうか。
1 使い込み時期による場合分け
(1)被相続人が亡くなる前に預金を引き出し、使い込んでいる場合
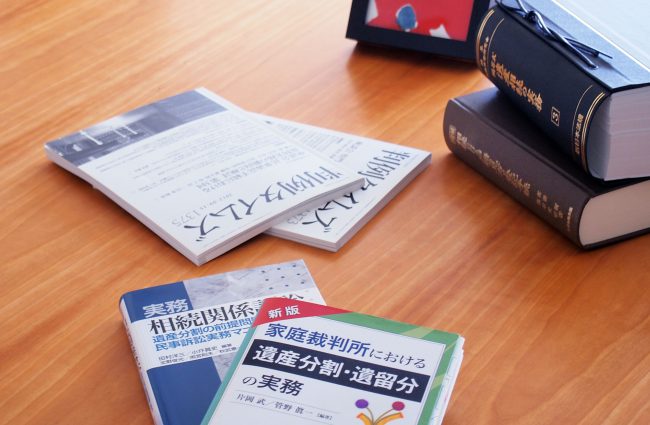
預金の引き出し行為が、被相続人の意思に基づいて行われている場合には、それは現金の贈与にあたりますので、特別受益にあたるのではないかが問題となります。
特別受益にあたる場合には、引き出された預金分を相続財産に加算して、それぞれの相続分を計算することになります。
一方、預金の引き出し行為が、被相続人に無断で行われている場合には、被相続人は預金を引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有しますので、各相続人は法定相続分に従ってその請求権を相続することになり、預金を引き出した相続人に対して返還を求めることができます。
(2)被相続人が亡くなった後に預金を引き出し、使い込んでいる場合
被相続人の預金は、遺産分割協議を待たず、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に従って当然に分割されます。従って、相続人の1人が、自分の法定相続分を超えて預金の引き出しを行えば、他の相続人に対する不法行為又は不当利得となりますので、他の相続人は、預金の引き出しを行った相続人に対し、預金の返還を請求することができます。
2 預金の返還を求める方法
預金の引き出し行為は、遺産分割協議の中で争われますが、上記のように、特別受益にあたるかどうかが争われるケースを除いては、法的には遺産分割の問題ではなく、不法行為または不当利得の問題です。
従って、遺産分割協議の中で解決できればそれでよいのですが、相続人間で協議がまとまらない場合には、遺産分割調停ではなく、預金の引き出し行為だけを別個にして民事裁判等の手続で解決を図ることになります。
具体的には、損害賠償請求訴訟、不当利得返還請求訴訟等の手続が考えられます。
3 預金の返還を請求するために必要な資料
預金の返還を求めるには、次のような事実が必要であり、その立証のための資料が必要になります。
(1)相続開始前に預金を引き出している場合
① 預金の引き出し行為を行ったのはだれか。
→預金の引き出しについて認めていることが分かる資料
② 預金の引き出し行為が被相続人の意思に基づいて行われているかどうか。
→贈与契約書、預金の引き出し指示メモなど、被相続人の意思が現れている資料
被相続人の納税資料、施設利用料領収書など、預金の使途が分かる資料
③ 引き出された預金額はいくらか。
→預金の取引明細書、通帳など
(2)相続開始後に預金を引き出している場合
① 相続開始時の預金額・引き出した預金額はいくらか。
→預金の取引明細書、通帳など
② 預金の引き出し行為を行ったのはだれか。
→預金通帳、キャッシュカード等の管理者が誰であるかを示す資料
預金の引き出し行為は、一般の方は相続問題の一環であると考えることが多いと思いますが、法的には相続とは別問題であることが多く、引き出した相続人が引き出したことを認めなければ、遺産分割とは別の民事訴訟手続等で争わなければなりません。
遺産分割調停とは別個に裁判を行うのは、手続的にも費用的にも負担であり、この点を踏まえて当事者間で和解協議を進めるのが望ましいケースが多く見受けられます。
遺産分割とは種類の異なる難しさがありますので、弁護士へのご相談をお勧めします。