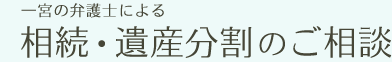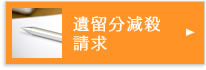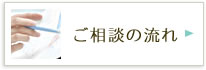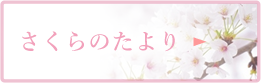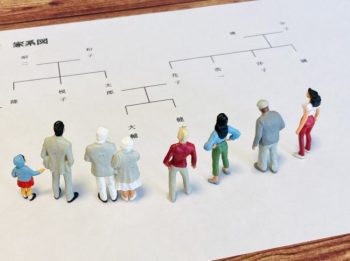(1)特別受益とは
相続人が複数いる場合に,そのうちの一部の相続人が,生前に被相続人から不動産やお金の贈与を受けている場合がありますが,そのような場合に相続財産を均等に分けると,生前の贈与を受けていた相続人だけが得をする結果になります。
このような不公平を避けるために設けられているのが「特別受益」の制度です。
特別受益が認められるケースでは,特別受益分を相続財産に加算したものを相続財産とみなし,贈与を受けていた相続人は遺産を先取りしたものとして相続分を計算します。
例 相続人が配偶者と子ども3人
配偶者が相続開始前に自宅不動産(1000万円)を贈与されている
相続開始時の相続財産の総額は5000万円 のケース
相続開始時の財産(5000万円)+特別受益(1000万円)=6000万円
子どもの相続分
6000万円×1/2×1/3=1人当たり1000万円
配偶者の具体的相続分
6000万円×1/2-1000万円(特別受益分)=2000万円
(2)特別受益にあたるもの
ではどのようなものが特別受益にあたるのでしょうか。
民法では,①遺贈,②婚姻・養子縁組のための贈与,③生計の資本として受けた贈与が特別受益にあたるとされています。
③の生計の資本として受けた贈与にあたるかどうかが争われるケースが多数ですが,相続人の一部だけが高い学費を出してもらっている,居住用の不動産を贈与されている,事業に必要な資金・不動産などの提供を受けているなどの例で特別受益性が認められています。
(3)特別受益の持ち戻し免除
特別受益と認められるケースでも,被相続人の意思表示により,特別受益が遺産に持ち戻すのを免除される場合があります。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
書面などで明示して意思表示されていることはめったになく,黙示の意思表示が問題になるケースが一般的です。
例えば,障害のある子どもにまとまった生活費を渡しているケースや,長年同居していた相続人に自宅を無償で使用させてきたケースなど,他の相続人との公平を考えて,被相続人としては持ち戻しを免除する意思であったと推測される場合には,黙示の持ち戻し免除の意思表示と認められます。