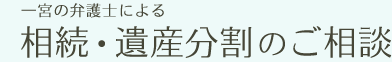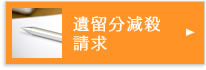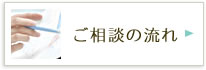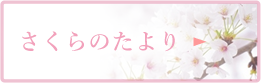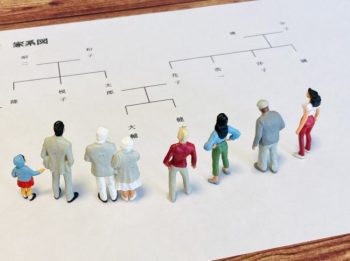(1)寄与分とは
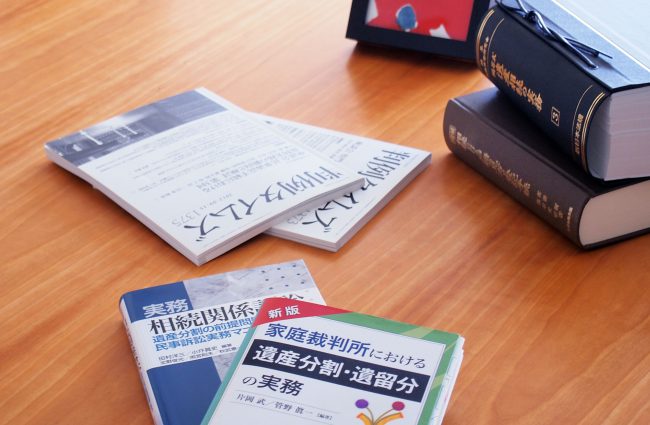
寄与分とは,相続人の中に被相続人の事業に関して労務の提供・財産上の給付をし,または被相続人の療養看護等によって,被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)をしたと認められる者がいる場合には,その貢献に応じて相当額の財産を相続分に加算して取得させるという制度です。
(2)寄与分と認められるための要件
寄与分と認められるには,次の要件を満たす必要があります。
① 相続人の行為であること
相続人間の公平を図るための制度ですので,相続人の行為であることが必要です。
ただし,相続人の配偶者や子どもが寄与した場合で,それが相続人自身の寄与と同視できるような場合には,寄与分が認められる場合があります。
② 特別の寄与であること
被相続人と相続人の身分関係に基づいて、通常期待されるような程度の貢献を超えるような貢献が必要だとされています。
例えば,夫婦や親子の間で介護が行われたとしても,それが夫婦,親子間であれば当然とみなされるような行為であれば,特別な寄与とは認められません。
また,家業を手伝っているケースでは,無償であることが必要とされ,給与や生活費を出してもらっているなどの場合には特別の寄与とは認められないのが一般的です。
③ 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
被相続人の財産の減少が防止され,または財産が増加した場合でなければ寄与とは認められません。財産上の行為がない行為は寄与行為には当たりません。
④ 寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係があること
被相続人が落ち込んでいるときに励ました,などのように精神的な効果しかなく,財産的な効果がない行為は寄与行為とは認められません。
(3)寄与行為の代表的な種類
① 家事従事型
家業である農業,商工業などに従事してきたという寄与行為です。
無償で従事してきたこと,継続的に従事してきたこと,専従してきたこと,特別の貢献を果たしてきたことなどが要求されます。
② 金銭等出資型
被相続人に対して住宅購入資金を援助したり,医療費などの負担したりなど,財産的な支援をしたという寄与行為です。
③ 療養看護型
相続人が被相続人の介護,病気療養に従事したという寄与行為です。
親族間では本来互いに支え合うべきものですので,特別の寄与というためには,無償性,継続性,専従性,特別の貢献性などが要求されます。
④ 扶養型
相続人が被相続人を扶養してきたという寄与行為です。
親族間では本来互いに支え合うべき者ですので,特別の寄与というためには,無償性,継続性,特別の貢献性などが要求されます。
⑤ 財産管理型
被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与したという寄与行為です。
不動産の賃貸管理を行ってきたというケースがよく見受けられます。
特別の寄与と言うためには,無償性,継続性,特別の貢献性などが要求されます。
上述のように,そもそも親族間では互いに支え合うべきものであるため,寄与分の認定に裁判所は慎重です。また,寄与行為の当時は相続時に返してもらおうなどと考えていないため,寄与行為を行ったことを立証できないケースも多くみられます。
寄与分を主張する場合には,自分にどれだけの犠牲があり,被相続人にどれだけの利益があったのかをできるだけ客観的な資料で説明できるよう準備が必要です。