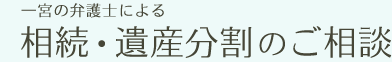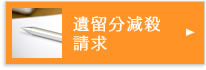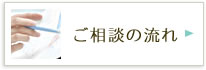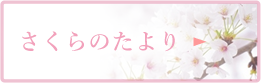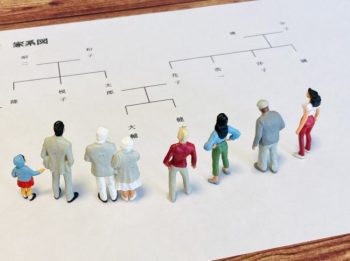相続の流れ
 被相続人がお亡くなりになったあと、相続の手続はどのように行われるのでし ょうか。
被相続人がお亡くなりになったあと、相続の手続はどのように行われるのでし ょうか。
時系列に沿って手続の流れを見てみましょう。
①被相続人の死去(相続開始)
・通夜、葬儀、告別式などが行われます。
・葬儀に要した費用の明細は領収書とともに取っておきましょう。
②7日以内
被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出しましょう。
③14日以内
・住民票の世帯主変更届を提出します。
・銀行等に相続開始の連絡をして、銀行預金の封鎖、公共料金などの各種名義を変更します。
・亡くなられた方のご自宅などに遺言書が保管されていないか、公正証書遺言が作成されていないかを確認します。相続人であれば、全国どこの公証役場でも、公正証書遺言が保管されているかどうかの確認ができます。
④3ヶ月以内
相続放棄・限定承認を行うかどうかの期限です。単純承認を行うべきかどうか判断できない場合には、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所へ伸長の手続を行うことによって調査期間を延長することができます。
・戸籍を調査して相続人が誰なのかを確認しましょう。相続人に漏れがあると、遺産分割協議書が無効になりますので、相続人調査は慎重に行いましょう。
・相続財産(預金・現金・不動産・車・高価品など)・負債(住宅ローンなど)を調査しましょう。
・負債が多いと予想される場合には相続放棄・限定承認の手続をしましょう。
⑤4ヶ月以内
被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)
非相続人がお亡くなりになった年の1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。
⑥10ヶ月以内
・被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
この期限内に申告・納税をしなかった場合は、加算税・滞納税が課されますので注意が必要です。
・早急に相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、預金や不動産の名義変更に必要になりますので必ず作成しましょう。
・協議書に従って財産の名義変更をしましょう。
名義変更は法律で義務付けられている訳ではありませんが、次の相続が発生して権利関係が不明になってしまったり、売却などの処分が難しくなったりしますので、早めに名義変更することをお勧めします。
⑦12ヶ月以内
遺留分減殺請求の期限です。
1年を過ぎると請求できなくなりますので、自分の遺留分が侵害されていることを知ったら、早急に遺留分減殺請求の手続を行いましょう。
遺産分割の流れ
 相続が開始した後,相続人は具体的にどのように遺産分割の手続を進めればよいでしょうか。
相続が開始した後,相続人は具体的にどのように遺産分割の手続を進めればよいでしょうか。
遺産分割には4つのケースがあります。
1 遺言による指定分割
まずは遺言があるかどうかを確認しましょう。
遺言によって遺産分割の方法が具体的に指示されている場合には,それに従って遺産が分割されます。
ただし,相続人全員が合意すれば,遺言の指示に反する分割方法によることも可能です。
2 相続人全員による協議分割
遺言がない場合には,相続人全員で協議して分割方法を決定します。
相続人の一部が欠けた状態で協議しても有効な協議分割になりませんので,必ず全員で協議する必要があります。
後になって紛争にならないよう,協議がまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。
協議に従って金融機関で預金の名義を変更したり,法務局で不動産の名義を変更する場合には,相続人全員の印鑑証明書と実印が押された遺産分割協議書が必要になります。
3 調停分割
相続人間で遺産分割協議がまとまらず,遺産分割ができない場合には,遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて,裁判所を通じて話し合いましょう。
裁判所の調停によって行われる遺産分割を調停分割といいます。
4 審判分割
調停でも話し合いがまとまらず,遺産分割方法が決まらない場合には,審判という手続に移行し,最終的には裁判所が遺産分割方法を決定します。これを審判分割と言います。
ただし,遺言書が有効かどうか,ある財産が遺産に含まれるかどうかなど,訴訟によらなければ確定することができない問題もありますので注意が必要です。