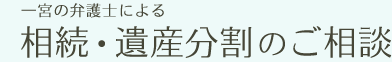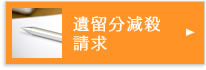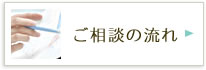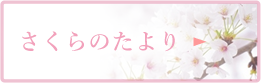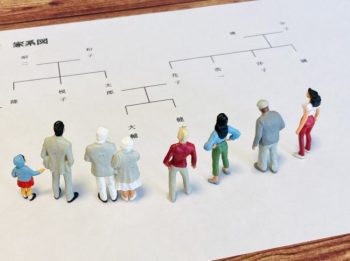1)遺留分の割合

被相続人は遺言によって,自分の財産を死後どのように分配するかを決めることができます。
ですが,生前被相続人の財産形成に協力してきた家族を無視して,例えば不倫相手に全部遺産を遺贈してしまったり,慈善団体に寄付してしまったりすれば,残された法定相続人にとってあまりに不公平です。
そこで民法は,法定相続人ごとに「遺留分」という遺言によっても侵害されない持分を定めました。
直系尊属のみが相続人の場合→相続財産の3分の1
その他の場合→相続財産の2分の1
*ただし兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分権利者が数人ある場合には,上記の遺留分を各相続人の法定相続分に従って分けます。
例 相続財産1000万円,相続人は配偶者と子ども2名
遺言により相続財産すべてを第三者に遺贈してしまったケース
遺留分=1000万円×1/2=500万円
配偶者の遺留分=500万円×1/2=250万円
子どもの遺留分=500万円×各1/4=125万円
(2)遺留分の請求方法
遺留分が侵害されていても,遺言の内容が当然にその部分だけ無効になるわけではありません。遺留分の侵害を争いたい場合には,遺留分を侵害している相手に対し,遺留分減殺請求権を行使するという意思表示をしなければなりません。
遺留分の額がいくらで,何を請求するのか明示する必要はなく,単に遺留分減殺請求をすることが表示されていれば足ります。
(3)時効
遺留分減殺請求権には期限があります。相続が開始したことと,遺留分を侵害されたことを知った時から1年間これを行わないとき,もしくは相続開始の時から10年を経過したときには時効によって消滅します。
遺留分減殺請求の方法には制限がなく,裁判上でも裁判外でも,書面でも口頭でも良いのですが,後になって時効期間内に意思表示したことが分かるよう,配達証明書付内容証明郵便で行うのが良いでしょう。