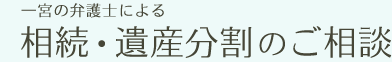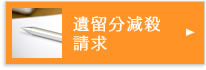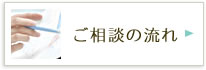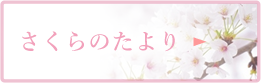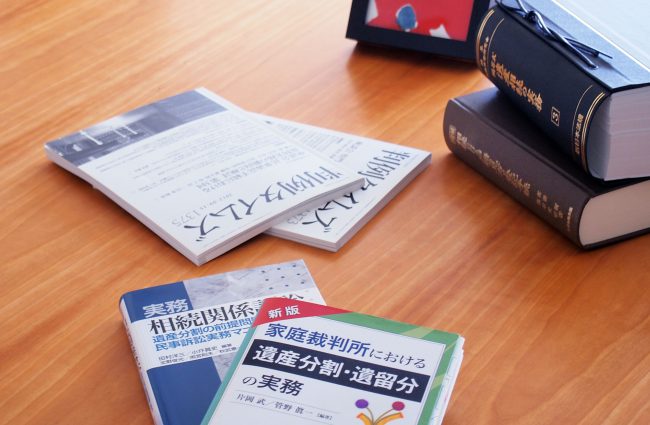
成年後見を弁護士などの専門職後見人に依頼する際、おそらくだれもが、
「財産をすべて他人に預けて大丈夫だろうか」
「不正に使用されてしまわないだろうか」
と不安に感じられるのではないかと思います。
この点、最高裁の調査によれば、2010年6月から2012年9月までの間に発生した成年後見人による財産横領などの不正件数は898件にのぼり、被害総額は83億円と、非常に憂慮すべき状況であることが判明しました。
上記不正件数のうち、98%は、親族が後見人であったケースであることが明らかとなっています。
大変残念なことに、弁護士、司法書士など、専門職後見人による横領事件も散見されるのですが、親族後見人が後見人全体の42%であることからすると、不正事案の98%が親族後見人であるという数字は、親族後見人による不正が極めて多発していることを示しています。
こうした状況には、日本の古くからの慣習が影響しているとみられます。
つまり、日本には家を継ぐ者がその家の財産をすべて継承するという考え方がまだ根強く残っていることから、親の後見人となった子ども等が、「親の財産は自分の財産」という考えに基づいて、それほど悪意なく、管理していた被後見人の財産を、当然のように自分のために使用してしまうというケースが多くみられるのです。
これに対し、専門職後見人は、職業上の良心と責任に従って業務を遂行しています。また仮に横領などの不正行為を行えば、資格を喪失する危険という大きなリスクも負っています。
さらに専門職後見人の場合には、業務上の賠償保険(※)に加入している場合もあり、親族後見人による不正のケースとは異なり、被害も回復されやすいと言えます。
このため現在の家庭裁判所は、積極的に専門職後見人を選任する方向に方針を変更してきているのです。